特集
SPECIAL
- 記事企画
- ボトムズ流仕事術
【第13回】“アンチ天才”のボトムズ流仕事術
ヤマトに負けて、ガンダムに負けた
今⽇から始める「敗者復活」~“アンチ天才”のボトムズ流仕事術・2
2008年9⽉10⽇(水) 渡辺由美⼦
―― 前回は、⾃分の⼒量を⾼く評価しすぎると「負け感」からなかなか脱却できない、というお話でしたが、⾃分の⼒量というのは、なかなか正確にわからない気がします。
担当編集・Y …そういえば昔、どなたか落語家さんがおっしゃったことで、「⼈の噺を客として聞いてみると、俺よりちょっと下⼿かなと思うとだいたい⾃分ぐらい。俺と同じくらいかなと思うとかなり上を⾏かれていて、こいつはうまい! と思ったら、もうはるか上⾏っていると思った⽅がいい」という話が。
⾼橋 ああ、それは⾯⽩いですね。確かにそうですよね。同じぐらいかなと思ったら、実は相当上⼿いというのはあるな、確かに。
僕ね、たぶんやっぱり⼈間は基本的に⾃分に⽢いんだと思うんですよ。それだけだと思うんです。やっぱり⾃分は⾃分に⽢いんですね。
Y ⾃分に⽢いのが⼈間の基本。だとしたら、「⾃分の⼒を冷静に測る」というのは、つまりはどこか、市場なり、競技場なりに⾏って、値付けをしたり勝負をして、なんらかの結果が出てようやく納得できることではないのかな、と。
―― それなら私、なおさら⾃分の⼒量なんて正確に測りたくない気がします(苦笑)。「負け感」を感じている⼈が⾃分の⼒量を測ろうとするのは、「⾃分が他⼈と⽐べて負けてることを、決定的に認識する」という話になりますよね。それはしんどいと思うんです。
負けたときに、楽になるには
Y いやいやいや、だから……何か、いい負け⽅というのがありそうな気がするんですけどね。⾼校のころ柔道の授業で、⻘畳にばしんとたたきつけられる経験をしたときに、「投げられたのになんだか気持ちいい」と感じたことがあるんです。
市場なり、競技場で負けたら、もちろんおっしゃるとおり敗北に深く傷つくんですけれど、何かそこから、「じゃあ次はこういう練習をしてやろう」でもいいし、「柔道ってやっぱり⾯⽩いなあ」でもいいし、「柔道もうやめようかな」でもいいですけれど、「負けた」こと⾃体に固着しないで済むような負け⽅があったら、⾃分の値付けを試すこと、知ることがちょっと楽に出来るかな…と。
⾼橋 そういうことなら「負けたら、とにかく相⼿を認めちゃう」というのは、楽ですよ。アイツはすごいと。その時にもう認めちゃう。何というのかな、条件をつけないで、取りあえず認めちゃう。
―― 「負けたら相⼿を認める」のは、楽なんですか!? 悲しくならないですか?
⾼橋 僕もね、いろいろあるんですよ。勝ち負けでいうと。
僕は「ゼロテスター」(1973年)が初監督だったんですけど、その時の僕の監督業に対する評価は決して悪かったわけじゃないんですよ。オリジナル作品で1年以上続きましたから。70本ぐらい作りましたね。
だけれどもその当時、途中から「宇宙戦艦ヤマト」(74年)が放送され始めて。
「同じスタッフなのに…!」――「ヤマト」の第1話に打ちのめされる
―― えっ……! 「ヤマト」ですか!? アニメファンを⼤量に⽣み出して社会現象にもなった。あれが同時期に。
⾼橋 「宇宙戦艦ヤマト」は、本放送のときには数字的には26話で打ち切りでしたから、視聴率とかそういうことで⾔えば負けではないんですけど、第1話を⾒たときに「内容的に負けた」と思ったわけですよ。
というのは、「ヤマト」のチーフディレクターは、「ゼロテスター」でも外注で絵コンテをお願いしていた⽯⿊昇さんですからね。僕らの仲間内もみんな「ヤマト」に関わっているわけですよ。「ゼロテスター」で⼀番コンテを描いてくれたのは、たぶん安彦良和さんなんですけど、安彦さんは「ヤマト」でも⼀番たくさん絵コンテを描いているわけです。
―― 「ヤマト」を作っているスタッフは、監督の「ゼロテスター」でも⼀緒に組んでいたスタッフだったんですね。
⾼橋 ええ。最初の頃は視聴率的に僕らの⽅が勝っていた。商業的にも途中までは勝っているわけです。けれどもそういうことじゃなくて、「ヤマト」の第1話が放送された段階で、ああ、同じスタッフと組んでいながら、作品的に負けていると。要するにそれはもう⾃分としては、監督の資質ということに関して⾃分で「また」疑問を持つわけですよ。
Y 「また」と仰ったのは、⾍プロ時代に周りと⽐べてご⾃⾝が「天才ではない」と思わされたというお話ですよね。そうなると、監督は「ヤマト」にも撃沈されていたんですか。
⾼橋 そうなんです、「ヤマト」に撃沈、実はその後にもう1発、「サイボーグ009(新)」(79年)を監督したときには、「機動戦⼠ガンダム」(79年)に撃沈されてます。
Y …それは、しかし…何というか、もうどうしようもないですね。アニメに興味がない⽅には、⾃動⾞業界だったら、新⾞を出したとたんにプリウスが、電機業界だったらiPodが出てきた、みたいな感じでしょうか。後から考えたら相⼿が悪すぎる。
とはいっても「ヤマト」「ガンダム」は、どちらも最初の放映時は視聴率がまったく振るいませんでしたが。
⾼橋 それは世の中がすぐ追いつかなかっただけであって、作り⼿としてあのすごさが分からないようだったら、それは勝ち負けどころじゃなくて、監督としてどうしようもないでしょう、きっと。
Y あの⼆作品を「歴史に残る作品だ」、と感じられないわけですから、そうなのでしょうね。ただ、企画⾃体は「ヤマト」も「ゼロテスター」も、企画とかプロデューサーとか、上の誰かが持ってきて始まるものですよね。
⾼橋 そうですね。
Y だとしたら、たまたま制作を許す舞台装置があったか、許さない舞台装置だったか、それだけだろうというふうにも考えられますね。
予算や状況は⾔い訳にならない
⾼橋 いや、それは全然違います。監督として、作り⼿としての映像のテクニックとか、⼀つ⼀つを⽐べたところで全部向こうの⽅が上なんですよ。
僕らにもテクニックがなかったわけじゃない。けど、僕らは⾃分たちのいままで持っていたものを越えた表現をやらなくて、向こうはやっちゃったと。結果としてフィルムの上に定着した⽅が、圧倒的に勝ちです。どこでその差が分かれるかは今でも分からないんですけれども、⾔い訳は効かないですよね。プロデューサーがこうだからとか、局がこうだから、予算がこうだからということはあんまり。それは明らかに⾔い訳の⽅が強いですから。それは⾃分が⼀番分かることですからね。
Y いや…そうなんですけどね。「⾔われた仕事をやっています」という⾝には厳しいお⾔葉です、それ。
―― それにしても、同世代には宮崎駿さん、出崎統さんがいて、初監督で「ヤマト」にやられ、⽴ち上がってもういちど挑んだら今度は「ガンダム」にぶつかったと……。すごい負け⽅をされたのですね。「もうやめた!」となりそうな。
完膚無きまでに負けておくと、次に⾏ける?
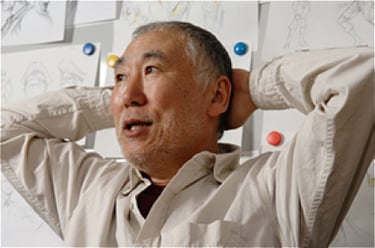
⾼橋 「もうやめた!」と、実はなったんですけど(笑)。
―― え?
⾼橋 でも、この「完膚無きまでの負け⽅」が意外とよかったんですよ。今考えると。
「こういう条件だったら勝てたかもしれない」とかいうのは、ちょっと負け惜しみに近いじゃないですか。負けはまるごとそのまんま認めちゃうと、実は「負け」を引きずらないで、次に⾏けるという気がしますね。
―― どういうことでしょう。監督はどうやって「もうやめた!」から「次」に⾏けたのですか?
(次回に続く)
※本連載は、2008年に公開されたインタビューのリバイバル掲載になります。







