特集
SPECIAL
- 記事企画
- ボトムズ流仕事術
【第15回】“アンチ天才”のボトムズ流仕事術
弱点という"呼び水"をうまく使おうよ
今⽇から始める「敗者復活」~“アンチ天才”のボトムズ流仕事術・2
2008年10⽉1⽇(水) 渡辺由美⼦
―― 負けて、苦しみに耐えるためにいったん「⼼のゆりかご」に⼊って、もう⼀度⽴ち上がる気⼒がわいたら改めて勝負に出ると。
⾼橋 その時はもう⾃分には⾜りないところがあるとわかってますからね。⾃分に⾜りない部分がわかると、勝つ⽅法はいろいろ⾒つかるわけですよ。
―― なるほど。
⾼橋 ⾜りない分は補えばいいんです。直接的な⽅法としては、⾃分で猛勉強をして補う。でも僕なんかは、勉強は嫌いだから(笑)、“外付けのハードディスク”で補うんですよ。要するに協⼒者を作るんですね。
―― 協⼒者?
⾼橋 僕はアニメを作っていて、どこかで⼀個の作家としては弱いな、と思うところがあるんです。漫画家とか⼩説家とか⾳楽家とかの個⼈で全うできるもの、個⼈でもって表現が完結する職業の作家性というのは、アニメよりどこか上位の感じがするわけですよ。彼らは作家として、僕よりもちゃんと完成しているというか、強⼒なエネルギーを持っているんだという⾵に思っているわけですね。
じゃあ、⾃分が個⼈で成⽴している作家よりは、エネルギーの総体も質も劣ると思った時にどうするか。ならば、さまざまな能⼒を持っている⼈たちの集合体といいますか、集団作業でやってみようと。集団作業ということの⼿間の掛かり⽅とか、⾯倒くささというのもまたあるはずなんですけれども、でも、⾃分でもって完全体でないと思ったならば、不完全な部分というのは外の能⼒をいろいろもらわないとできないわけでね。
テレビのシリーズアニメというのは集団作業で、1⼈で表現を完結させることができない⼈でも作品が作れるんですね。また、絵を描く⼈、背景を描く⼈、声を⼊れる⼈、それぞれのプロが担当することで、1⼈ではできないような表現が可能になる。集団でものをつくっていくには、みんなの意⾒を聞かなくてはいけないから、⼿間や時間がかかることも相当あるんですが、僕の場合は最初から覚悟していますね。その⾯倒くささは当然起こることで、でもそれは⾃分のためになるだろうと。
で、できたものの成果は独り占めしない(Part1最終回「7割で腹をくくって、⽣き残れ!」)。まあ、結果的に独り占めしちゃったのかな、と感じることもあるけれど、それはあえて拒まなくても良いんじゃないか(笑)と。
弱いところがいい効果を⽣む
⾼橋 集団作業で⼤事なのは、仲間と⼿柄争いをするんじゃなくて、協⼒していくことですね。
⼈間ってね、1⼈で何でも決めるというのは本当に⼤変なんですね。やはりちょっと⼈の考えに頼ってみるのがいいですよ。僕なんかはもうしょっちゅうですからね。
⼈の話もできるだけ聞く。もう⽿を傾けざるを得ないですよ。ひとりではできないんですから。
―― ⼈に頼ることは、⾃分のプライドを曲げることではないんですね。
⾼橋 僕の場合は、“弱点”が案外いい効果を⽣んでいると思うんですよ。
―― 弱点?
⾼橋 僕にはちゃんとした⼤⼈にない、恥知らずなところがあるんですよ。
よくアニメや雑誌でタイトルなんかの「題字」を頼まれることがあるんですけど、僕は平気で書いちゃうほうなんです。 すると「題字:⾼橋良輔」なんてクレジットが載って、ちゃんとした⼈からは怒られるわけですよ。
「題字は⽂字のプロが書くべきで、監督がほいほいアマチュアみたいな真似をしたらだめだろう」と。この業界には⼀芸を⼤事にしている⼈がいっぱいいますからね。プロとアマの線引きはものすごく厳しくするし、⾃分⾃⾝もその境界線をみだりに⾏ったり来たりしないんです。
ですから、僕のことをプロだと思ってる⼈は⾔いますよ。お前はいつまで経っても⼤⼈になれないし、恥ずかしくないのかと。
―― 60歳を過ぎて「⼤⼈になれ」と⾔われるというのも、ある意味すごいですね。
⾼橋 そうですねぇ。僕もたまに⾃分の意識を調整しなきゃいけないときがあって。
ちょっと前に、ヨーロッパでジャパニメーションのイベントを主催をしてくれた⼈たちが⽇本に来てくれたんです。みんなで⾷事をしようということになって、⽇本からイベントに⾏ったメンバーがほとんど集まったんです。
みんなアニメ業界の⼈なんですが、僕以外は、だいたい30歳前後なんですね。⼀番上でも40歳半ばまでいかないのかな。その中で僕だけがぴょんと20歳も⾶び抜けて年齢が上なわけ。
最初はそれに気づかなくて、気づいたのは散会のときの挨拶でした。みんな、僕には挨拶が丁寧なんですよ。
そこで、⼀緒に⾏った塚⽥プロデューサーが、僕に「ね、わかるでしょう、みんな、あなたが僕らとカラオケではっちゃけて遊んでいるのを知らないんだから(笑)」。普通の⼈は、あなたを40年間アニメを作り続けてきた⼤御所の監督として⾒るんですよ、と。
でも僕は、普段、⾃分がそんなに年⻑に⾒られているなんて思わないわけですよ。20代の⼈も、30代の⼈も、40代の⼈も、僕はそんなに気にしないで会ってしゃべっているから。
でも他のところに⾏ったときには、「60代で現役で監督やってる⼈」という接し⽅になるわけですね。
⾒せてしまえば、武器になる
⾼橋 僕の歳ではひな壇に上げられちゃうことの⽅が普通であって、今のワイワイ何でも話せる僕の周囲の環境というのは、恵まれ過ぎちゃってるのかな。今⼀緒に仕事している⼈たちは、僕に内緒にしていることもあるだろうけど、たいていのことは普通に話してくれますからね。僕にとってはそれがうれしいですね。
担当編集・Y もし「偉い⼈」という形でずっと接せられていたら、⾃分で⾃分を⾒失いそうになりますよね。「偉い⼈」の⽴場から遠ざかることで、他⼈に⼝を出させない、悪い点を指摘してもらえない、そういう危険性から回避できている、のでは。
⾼橋 そうですね。
―― 若い⼈が監督に話しかけやすいのは、アニメスタジオという場だからじゃなくて、若い⼈が話しやすい雰囲気があるからだと思うんです。
⾼橋 あと、分かりやすいんですよ、僕の弱点は。
例えば、よく働く⼈には弱点は⾔いにくいじゃないですか。でも、僕があんまり働かないと、スタッフから「もうちょっと働いてくださいよ」と声が⾶んでくる(笑)。働かないというのは、相⼿にすれば⼩⾔を⾔いやすいことなんでしょう。
技術的なことも、「これは俺、苦⼿だからやらない」とか⾔うと、「苦⼿なんて⾔ってられないでしょう︖」と怒られてみたりしてね(笑)。
わりかた粒⽴って、苦⼿なことや弱点が多いほうなんです。弱点って、本⼈が隠していると指摘しにくいじゃないですか。僕は、⾃分の弱点を弱点だと思って認識してるんだけど、結構恥知らずに表に出してるところがあって、周りの⼈も、その弱点を突いてもたぶんそんなに気にしないだろうなと、双⽅が了解しているんですね。
―― ―弱点をさらけ出すことで、年下の⼈でもフラットに、同じ⽬線で話をしてくれやすいということですね。
⾼橋 やっぱり“呼び⽔としての弱点”って必要だと思うんですよ。彼らが指摘してくれるのは、僕が⾃分で表に出している弱点だけじゃないですから。後ろのほうに、本当に気づかなきゃいけない何か別の問題点がくっついてますからね。⾔ってくれるとその問題点がちょっとだけわかるんです。
Y ⾃分が完璧だと思っている⼈って、話しかけにくいですよね。何を⾔って、どう怒るか分からないみたいな感じになりがちで。
⾼橋 だろうと思いますよ。ちょっと弱いところが⾒えるほうが、周囲も楽じゃないですか。
―― 弱点が間⼝を広げて、「気づかなきゃいけない点」を教えてもらいやすくしているんですね。弱点も使いようという。
⾼橋 かもしれないですね。でも、間⼝は広げるけど、相⼿が⾔うことの全部は聞けないんですよ、それは。
―― そうなんですか?
気づくために、批判は聞く。でも、そのとおりにする必要はない
⾼橋 プロフェッショナルな同業者からは「アマチュアみたいなことをするな」と、優しくじゃなく、かなりきつく⾔われるんですよ。でも僕は相当⾃分に⽢いですから。あまり⾃分をプロサイドに置かないんですね。もうこの商売は永遠のアマチュアでいいんだという気持ちがありますからね。
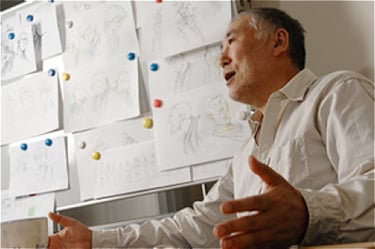
⾼橋 きつく叱られることの中に、反省材料というか、⾃分を⾒る座標ができるから、ありがたいとは思っているんです。でも、やっちゃうんですよねぇ。その忠告を胸の中にしまいつつですね。
「そういう価値観もあるんだな」と気づくことができる。でも、気づくというところで留めておく。いろいろな価値観があって、その中で⾃分はどの価値観で⽣きているかという⾃分の座標を確認するだけで。
いろいろな意⾒が存在していて、その中で⾃分の認める意⾒もあるんですけど、全部⼈の⾔う通りには⽣きられない。そう⼼の中で思い定めている。そこが⾃分の中にある「⾜がかり」なんでしょうね。
―― 誰もが否定してもそこだけは⾃分の考えを変えられない、というところが、⾃分だけの「⾜がかり」だと。だから「褒められることに罠がある」と疑うのと同様に、叱ってくれる⼈の意⾒も全部は聞けないということですね。
⾼橋 僕⾃⾝はそういうふうにしていますね。
⾃分⾃⾝が本当に譲れない点を⾒つけるためだけでも、他⼈からいろいろ突っ込んでもらう意味はあるんじゃないでしょうか。
(次回に続く)
※本連載は、2008年に公開されたインタビューのリバイバル掲載になります。







