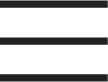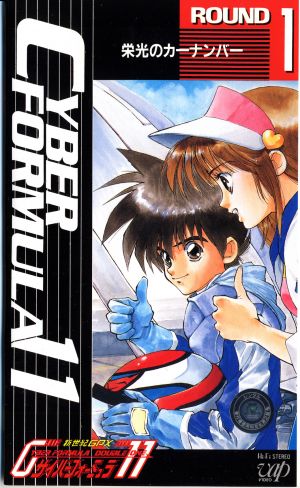特集
SPECIAL
- インタビュー
サンライズワールド クリエイターインタビュー 第23回
メカ作画監督 重田智
サンライズ作品のキーパーソンとなったスタッフに自身の関わった作品の思い出を語ってもらうクリエイターインタビュー。今回は9月に『重田智WORKSメカニカル画集』を出版する、メカ作画監督の重田智さんが登場。『新世紀GPXサイバーフォーミュラ』のOVAシリーズや『GEAR戦士電童』などの作品に関わった思い出を語ってもらった。
――重田さんがサンライズでお仕事をするきっかけは、どのような形からだったのでしょうか?
重田 最初の仕事は『機動戦士Zガンダム(以下、Zガンダム)』の第2原画としての作業ですね。当時は草間アートという作画スタジオで仕事をしていたんですが、そのスタジオで隣の席の先輩が、『Zガンダム』や『機動戦士ガンダムZZ(以下、ガンダムZZ)』のメカ作画監督をやられていた内田順久さんと知り合いだったんですよ。その方にメカ作画に興味があるという話をしているうちに「メカが描きたい奴がいる」という形で内田さんに紹介していただいたんですね。当時、草間アートでは、東映アニメーションや東京ムービー の仕事がメインで、週刊少年ジャンプ原作の『銀牙 流れ星銀』や『聖闘士星矢』などの作画に関わっていたんですが、『宇宙戦艦ヤマト』に憧れて業界に入った自分としては、「やっぱりメカが描きたいな」と思っていたんです。その後『ガンダムZZ』でも何回かお仕事をやらせてもらっているうちに次のステップに上がるためにフリーランスになった方がいいだろうと。その頃、ちょうどサンライズでは『機甲戦機ドラグナー(以下、ドラグナー)』が制作中で、ストーリーの折り返しくらいからフリーの原画マンとして仕事をするようになりました。『ドラグナー』の後半の作画話数の中で何回かを担当している時の演出が福田(己津央)さんの担当で、それが福田さんとの最初の仕事になりましたね。
――その後振り返ると大きな出会いではあったわけですね。
重田 福田さんとはそこで何回か一緒に仕事をしただけで、その後自分は『機甲警察メタルジャック(以下、メタルジャック)』に参加して、福田さんは『新世紀GPXサイバーフォーミュラ(以下、サイバーフォーミュラ)』のTVシリーズの監督をやっていたので、別々の仕事をしている感じでしたね。その後、『メタルジャック』のプロデューサーがOVAの『新世紀GPXサイバーフォーミュラ11(以下、サイバーフォーミュラ11)』を担当することになって、またそこで福田さんに会うという感じで。望んだわけではなくて、なんとなくな流れでまた御一緒することになったんです。でも、『サイバーフォーミュラ』に関わり始めた当初は、「ロボットじゃないレースマシンはどうやって描けばいいんだ?」ってなってしまっていて(笑)。ポーズは取れないし、派手なエフェクトもないんですよ。だから、『サイバーフォーミュラ11』の時は何をどう描けばいいか全然判らなかったんですけれど、まさかその後の約8年間、90年代をずっと付き合う作品になるとは思ってはいなかったですね。
――仕事で関わる前のサンライズという会社にはどんな印象を持たれていましたか?
重田 サンライズに関しては、『勇者ライディーン』や『超電磁ロボ コン・バトラーV』などの作品は個人的に好きでよく観ていました。『無敵超人ザンボット3』や『無敵鋼人ダイターン3』も面白いと思っていましたね。今であればそれがサンライズという会社のカラーだと良くわかるんですが、当時はほかのロボットアニメを作っている東映と何が違うのかはあまりピンと来ていなかったですね。ただ、感覚的には東映のロボットアニメに比べると、サンライズの作品はよりロボットの戦闘シーンを描くことにこだわっていて、「もっとロボットが活躍すればいいのに」と思う当時の自分を含めた男の子の心を掴んでいた気がしますね。今になると、サンライズはロボットの戦闘シーンを多いと大変だろうに、「多少無理しても頑張ってやっている」という感じだったんだと思いますね。クオリティはともかく、溢れ出るやる気が画面から伝わってくる感じがして好きでしたね。その後、アニメーターとして福田さんと仕事をするようになって、『GEAR戦士電童』や『機動戦士ガンダムSEED』などで「ロボットの見せ方とはなんぞや?」と考えるようになった時には、福田さんとは世代が近くて観てきたものが一緒だったりするので、サンライズ作品としての描写の考え方はみなまで言わなくても判る……というところはあったと思います。
――実際にサンライズでお仕事をしてみた感想はいかがでしたか?
重田 『ドラグナー』からサンライズの仕事を始めたわけですが、自分ってフリーランスのいち個人でしかないんですよね。サンライズ全体から見たら数多くいるアニメーターの中で「あなたは誰?」って感じだったんじゃないかと思います。今のようにスタジオに席があるわけではなくて、スタジオMAXというフリーランスが集まるスタジオで仕事をしていたので、サンライズには打ち合わせで行く程度で、その頃に印象が大きく変わるようなことは無かったですね。時期的にも『Zガンダム』、『ガンダムZZ』、『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』と富野由悠季さんのロボットものが続いていて、これからもそのジャンルがずっと存在し続けると思っていたら、『ドラグナー』の後で1回プツっと切れてしまって。その後の『鎧伝サムライトルーパー』の作画ローテーションに入れてもらうのも大変でした。テレビアニメというのは、外側で受けてくれるグロス班という作画スタジオごとの付き合いというのが大きくて、そこから外れてしまうといち個人として仕事をするのがかなり難しいんだなとその時には感じていて、『サイバーフォーミュラ』でサンライズの中に入って仕事を始めるまではそう思っていました。だから当時は、こうやって取材を受けて「どうでしたか?」なんて聞かれるとは思ってもいなかったですし、それなりに長くやってきてわかるのは、福田さんをはじめ関わる作品とその環境に恵まれていて、作品がヒットしたから上手くいっているんだなと思うところがあります。アニメーターって、自分で何かをゼロから作り出しているんじゃなく 、作品の制作過程の一部に関わっているのであって、「原画で頑張ったんです」と言っても周りからはなかなか認めて貰えないんじゃないか。そういった難しさを改めて感じたりはしていましたね。
――ご自身で仕事をしていく中で、ターニングポイントになった作品はありますか?
重田 それが自分でわかったら苦労はないよと思っています(笑)。今度出る自分の画集で、サンライズで仕事をするきっかけとなってくれた内田さんと対談をさせてもらったんですが、その時に内田さんが「重田の絵をこの業界に入った時からずっと見ているけど、重田は『サイバーフォーミュラ』あたりから変わってきた感じがした」、「闇雲に描いているんじゃなくて、描き方がわかって変わってきたというのがそばで見てきたからわかる」と仰っていて。そうなのかなって思いましたね。
――ご自身ではあまり実感が無いんですか?
重田 自分でもそう言われたから思っているわけではないんですが、やっぱりそれまでの仕事では、「好きだから、描きたいから、描けるから、その作品のメカを描かせてください」という感じで描いていたんですが、でも実際に描いてみると、思っているのとは違ってたりした絵は描いてないというか。この業界に入って仕事を始めてから「自分は絵の描き方をまったく知らないんだな」好きなのと描けるのでは全く別なんだなと痛感したんですよ。そうした暗中模索の中に『新世紀GPXサイバーフォーミュラZERO』 の時にプロデューサーから「あなたがメカ作画監督をやりなさい」と言われて、「自分がやっても大丈夫なのかな?」って思ったんです。アニメーターって昔は、仕事としてステップアップするにはある程度のラインがあって、それをクリアできたら原画から作画監督にあがれるような形だったんですね。だから、作画監督は自己申告でやりたいからやらせてもらえるものだとは思ってもいなかった。実際にメカ作監作業を始める時に「自分よりも上手い人が描いてくれたものを、どうしたらいいんだ?」と考えていたんですが、実際に作画監督として原画マンのカットをみて、その話数の中での全体バランスやシリーズを俯瞰してみる必要があるということを知ることができて、「この辺りの見せ場にウエイトを置いてやろう」とか作画のマンパワーのかけ方みたいなものがなんとなく判ってきたというのはありますね。
――立場が変化して、仕事の見え方が変わったわけですね。
重田 あとは『サイバーフォーミュラ』という作品は、レースマシンは基本的にはサーキットのコースに乗っていなければならないというのがあって。ロボットアニメだと空中や宇宙のBG(背景)上をFollowしていれば、アクションの見せ方は自由に描いて良しという世界なんですが、レースアニメは基本コースからはみ出してはいけないという世界なんですよね。それにグランプリごとにデザインされたサーキットがあって。サーキットやレースとかグランプリの雰囲気を出す事を含めて、それがレイアウト作業での縛りが多かったんです。だからかなり大変だったというのもあったんですが、逆にレイアウトをキチンとした意味合いを込めて画面の情報量をコントロールするというのをずっとやっていて。そうした作業が自分の仕事の仕方に大きな影響があったように思いますね。
――レースものは、視聴している側は試合の結果に向けた演出などで盛り上がりを体感できますが、描く側はそんなに多くのパターンは無いので見せ方が大変ですよね。
重田 結局、「走っていく」、「走ってくる」、「Followしている」の3つくらいしかないんですよね。ロボットのように何か格好いいポーズを決めるとか、ロボットの顔の作画が格好いいとか、必殺技が出て敵が爆発するとかはない。段取りや方向性に関しては福田さんが絵コンテでコントロールしてくれるんですけれど、実際レイアウトから作業を始めると絵面が似てしまって単調になってしまうんですよ。なので、作画的に見映えのするエフェクトを描くとか、タイミング的にもスピード感優先なのか、重量感のある見せ方なのか。またスピード感を追及していくとすぐにマシンがフレームからアウトしてしまうので、その後の間というか余韻を保たせるために火花を散らせるていて。それこそ、シリーズ中爆発やスパークよりも火花ばかり描いていた気もするんです。本当は内心ロボットアニメの方が作画的に自由度があって面白いだろうとは思っていたんですが、『サイバーフォーミュラ』でレースアニメの方に舵を切った時に学ばせてもらった事が自分のアニメーターとしての武器というかカラーになったのかなと思っていて。レースは基本的にはゴールに向けてマシンがみんな同じ方向に走る画面になるんですが、ロボットアニメでは敵対しているお互いが向かい合うことが多い。なのでレイアウト的にも絵の作り方や考え方が全然違うというところも大きな学びではありました。
――アニメーターとしての成長のきっかけにもなったんですね。
重田 アニメーターとして絵を描くこと、画面を作ることをどう考えて、どう処理して、フィルムで繋げたときにどう見えるのかといった事を考えることは、『サイバーフォーミュラ』で習ったことが大きかったですね。完全に掛り切りというわけではなかったんですが、関わっている期間が長かったということもあって、マシンレースの見せ方をシリーズごとにブラッシュアップできていって、ひとつのこと表現を突き詰めて描いていくということができたのも面白かったですね。また、いろんな人アニメーターの方のカットを見る機会も多かったですし。『サイバーフォーミュラ』では本当にいい経験が積めたと思います。
――『サイバーフォーミュラ』の後には、福田監督と一緒に『GEAR戦士電童』に関わられていますね。
重田 『GEAR戦士電童(以下、電童)』はテレビシリーズでしたけれど、今時のアニメの様に事前に全部完成納品してから放送枠を決めるのではなく、「撮って出し」ではないのですが、制作を放送日が追いかけてくるようなスケジュールだったので、優先事項となるのはとにかく各話数を作っていくことでした。そうなるとなかなかメカ作画そのものに拘ることがかなり難しかったですね。ストーリーの1クール目はデータウェポンの争奪戦、2クール目は輝刃の発現と凰牙の覚醒、3クール目はガルファとの決戦といった構成だったので最終回近くまでずっと電童の技のアクション、メカの発進、データウェポンの発現と武装形態、必殺技などのBANK/DNカットを描き続けていたという印象がありますね。そうしたパートに関しては福田さんが「それは重田さんのところに持っていって描いてもらって」と言われていたそうで。なので自分が担当したBANK/DNカットだけでもコンテの厚みが結構あって話数一冊分以上あったんじゃないかなと思います。
――ロボットを描くという部分では、『電童』で何か印象に残っていることはありますか?
重田 『電童』は、商品化に向けたメカデザインがまずあって、もともとのデザインはパワーで押すタイプということで手足のタービンが大きくてとにかくマッチョな雰囲気だったんですよ。福田さんとしてはアニメーションの演出上、もう少しスタイリッシュというかもう少しスマートな感じにさせたいという意向があって、そこで自分が電童と凰牙のプロポーションバランスをリライトすることになりました。さらに物語が中盤に差し掛かる頃に登場する、超獣王輝刃という新型データウェポンのデザインが元のラフのままだったのでそちらのリライトも担当したりと、結構メカ作監としての作業以外の仕事が膨大で大変だったという印象が強烈にあります。
――電童と凰牙は玩具の遊び映えとして、両手・両足が車輪のような形状になっていて、それを設置させていろんなスタイルで走行させられるというのがひとつの売りだったわけですが、その見せ方などもいろいろ悩まれたりしたのでしょうか。
重田 最初に玩具のロボットの両腕両足にタイヤが付いていて、それがいろんなポーズでの走行や大の字で回転するビデオを見せて もらったんです。それを見て「手足にタイヤが付いてるんですね」ってコメントしたら、福田さんの「俺は本編では“タイヤ”とは呼ばせない、あれは“タービン”で、タービンが回るとパワーが上がるんだ」という発言があって、その解釈はそのまま本編作画に活かされました。一方で、自分の方も膝立ちで走ってくるようなイメージの絵の発注があったんですが、ほかのロボットアニメではありえないかなり特殊なポーズになっちゃいますよね。脚のタービンを地面に接地させて膝立ちさせると当然背が低くなってしまうので、それを魅力あるスタイルで描くのが本当に難しかったです。電童や凰牙のシルエットやフォルムは勇者シリーズやガンダムの様なシルエットにエッジが立っておらず、肩アーマーが丸いフォルム、ウイングも付いてない、ライフルやシールドも持っていなくて、絵的に格好良く見せるのには苦労しましたね。
――電童はロボットデザインで映える「集中と拡散」がないシルエットですからね。
重田 デザインのリライトや本編のメカ作画を進めていくとロボットの格好いいと思われる部分の良いとこ取りを全部寄せ集めるとガンダムになるんだなと感心しましたね。自分としては仕事としての『電童』はすごく楽しかったし、描いていて面白かったんですよ。アニメーション的にも限られた時間の中で頑張ってやれたとも思いますし、アニメーションでの格好良さというのはデザインプラスアルファみたいなところがあると思うので、実際に画面で動いているところを観てもらって好きだし面白いと思ってもらえたらいいのかなと。そういったアニメーションとして頑張って創った結果からか、 今でも好きだと言ってくれる人がいるので、そこは本当にありがたいですよね。
――『サイバーフォーミュラ』や『電童』は今でも根強いファンに支持されていますね。
重田 それは『サイバーフォーミュラ』も『電童』も結果的に今だからそう言えるんじゃないかと思うんですよね。『サイバーフォーミュラ』をやっている頃は勇者シリーズが人気で、OVAの『新世紀GPXサイバーフォーミュラSIN』の頃には『勇者王ガオガイガー』OVAの制作が始まっていて、メカアニメーターはみんな向うに行ってしまっていて、正直羨ましいなという思いがありました。『サイバーフォーミュラ』も『電童』も企画やデザインの面である種の王道というかメインストリームに乗っていない作品という思いはありつつも、でもちょっとでも視聴者の方の目を引けるようにと思って描いてもいたし、自分なりに楽しんで描いていた部分には作画的内容にも多分プラスアルファがかなり入っていたんじゃないかなとは思いますね。厳密にコンテのオーダーに合わせて描くというよりも、アニメーターとしての自分たちが楽しんで「こうしたら興味を引いてくれるかな」と思って創った作品が、観てくれた人たちの心に何か残せたのだったら良かったと思います。
『機動戦士ガンダムSEED』のシリーズ以降の話は「ガンダムインフォ」に掲載していますので、そちらもあわせてせてお楽しみください。
ガンダムインフォ「重田智さんインタビュー」はこちらから>>
重田 智
アニメーター。千葉県出身。草間アートを経てスタジオMAXに所属。1985年『はーいステップジュン』で動画デビューし、『銀牙 流れ星 銀』で原画デビュー。『新世紀GPXサイバーフォーミュラ』OVAシリーズ、『GEAR戦士電童』、『機動戦士ガンダムSEED』シリーズ、などサンライズ作品のメカニカル作画監督をつとめる。