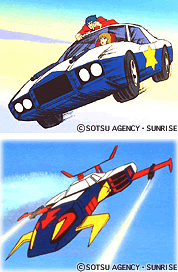特集
SPECIAL
- インタビュー
【第04回】リバイバル連載:サンライズ創業30周年企画「アトムの遺伝子 ガンダムの夢」

その4「サンダーバードがお手本」
創業者の一人[沼本清海]氏に会うため私たちは西武新宿線高田馬場駅に集合した。駅至近にある栄通りという繁華街……というより多少ピンクがかった飲食店街の一角、神田川沿いのビルの中に沼本氏の経営する株式会社3Dプラネットはある。氏は創業の“七人のサムライ”の1人であったが、[ゼロテスター]企画時に早々と袂を分かちメーカーサイドに転進を図っている。その後においてもサンライズとの交誼は深いものがあるが、退社のいきさつ、創業時の空気感などを聞くためにインタビューを申し込んだ。インタビューは、「高田馬場にアニメ関係者がスタジオを作ったのは僕が主宰していた[スタジオあかばんてん]が最初なんだよねー」 という私のしょむない自慢話から始まった。ま、それはむろん、沼本氏によって黙殺された。ま、ま、めげずに行きましょう。さて…、
高橋「あの時期にサンライズを創ろうというのは、結局虫プロが怪しくなったからですよね。今まで話を聞いてきているところでは、虫プロはこのままでは立ち行かないだろうから、アニメーションに入った連中がアニメで食っていくための場所、もしくは会社を作ろう言うことがきっかけですね」
沼本「いやあ、そうじゃないんだよ」
高橋「そうじゃない?」
沼本「連中は虫プロのスタッフに対して、虫プロ分割論というのを提案したのね。それ、山浦さん、言わなかったの?」
高橋「いや、そういう言い方ではないんですが、山浦さんは、経営陣が総退陣して現場だけ残してやれば、経営は再建出来るんじゃないかという提案をしたんだけども川畑さんが、あの時期の社長ですね、そういう変革論には全然のらなかったんで、このままではダメだろうと……」
沼本「それは、手塚及び経営スタッフに責任を取ってもらって、スタッフを連れて出ていってやれるところでやれば、あの時期そうやれば救済できると。あの時はフジテレビとかそういうところが応援しれくれるという話しもあったというような……ね。いろいろあったんだけど、それが出来なくて、まあそれではということでね、動いたということなんだけどれも。僕は、実はね、7人の中で一番最後に加わったんですよ」
高橋「あ、そうなんですか」
最後に加わって最初にやめたんですかってツッコミを入れそうになったが怒られそうなので我慢した。沼本氏は今では数少ない僕にとって散々世話になった怖い先輩なのである。
沼本「その頃、虫プロでは[哀しみのベラドンナ]をやってたんだけど、それをやってることが、どうみても金は使っても作品は良くならないと‥‥スケジュールを延ばし延ばしね、金を使えるだけ使うというやり方で、もう、こりゃあしょうがねえなと。で、直しのリテークっていうのが、その頃、僕が作画の方を全部面倒みてたからくるわけ、ワンサカ! 理不尽な、ギャアギャアギャアギャうるさいことが全部来る。それでもう俺やりたくねえって、それで辞表書いて、行かなかったんだ会社に。……そういうところに話がきたわけ」
沼本氏は私が虫プロに入社したときはアニメーターで動画の課長をしていた。歳は私とひとつしか違わないのに収入は3倍もあった。だから、よく飲みに連れていってもらったものである。酔った挙句に氏の下宿に泊めてもらって、極々芸術的なヌード写真集を拝見するのが楽しみだった。氏の名誉のために付け加えるが、それは絵の修行に役立てるためのそれはそれは高価な洋書の芸術的な写真集ではありました。
サンライズのオリジナルの源流
これははっきりしている
沼本「サンライズスタジオの立ち上がりというのはきっちゃんと俺と丸たんと。丸たんはまあシナリオだから仕事を上げたら持ってくるぐらいで、常時っていうか、一番スタジオに居たのが半藤だよ。きっちゃんが制作やって、文芸を丸たんがやって、作画以降の仕上げまで俺がやって、半藤が背景やるという状況で[ハゼドン]をやっていた」
高橋「じゃあ、創映社の方じゃなかったんですか沼本さんは」
沼本「いや、創映社は創映社。みんな創映社。きっちゃんも創映社だから。2つに分けないとヤバイっていうのがあって‥‥やったことはみんなサンライズスタジオの仕事なんだ創映社とはいっても」
高橋「僕は岸本さんは創映社の社員じゃないと思ってた。創業の7人は仲間としての7人で、創映社側にはお前行けと。こっちはこっちで現場はやっているからと。いずれ時がくれば‥‥そういう感じかと思っていました」
沼本「きっちゃんも一緒、創映社。まあ会議の時は7人が雁首揃えて伴次郎社長のところへ行って説教聞いていたんだ。まあそういうことで、だから将来に対する展望がなかったってことで、虫プロにおけるね、それでやめたということで、特別どうこういうわけじゃない。誰でもみんながさ、やっぱそうなればそうするだろうという、ごくごく普通の。特殊な形ってなんにもないよ」
高橋「沼本さんはその創映社もサンライズスタジオも結構早くやめてしまった。どの時点でやめたんですか。ゼロテスターの製作が始まる前にやめた?」
沼本「うん。企画を全部やり終えて」
高橋「その辺りのところをもう少し聞かせてください」
沼本「ジョン・ゲノワかデドワか忘れちゃったけど[サンダーバード]のメカデザインやったのがいたの。で、[ゼロテスター]では一応まとめて僕がメカデザインを代行して、あの時タツノコにいた作画の箕輪氏とか[スタジオぬえ]ラインと接点もってやりだしたということからが始まりで。その時ぬえはまだ[クリスタル・アート]になる前、SF同好会の連中だった。で、池袋の喫茶店に集めて“コーヒーとケーキぐらいは面倒見てやるからSFについて色々語ってくれ”って。うわーっと30人ぐらい仲間が来て、で、ぺらぺらしゃべらせた‥。そういう経緯がある」
高橋「最初の頃東長崎にスタジオとか集まり場所、作りましたね」
沼本「あの前。‥‥それでまあ、ぬえの連中に講義した。講義したのは何なのかというと、虫プロで合作を作ってた頃そこで作画の養成所もやった。その時に日本で絵を教える理論的な本がなかった。それで洋書を買ってきて翻訳して、それで理論をマスターした」
高橋「沼本さんが?」
沼本「そう、そういう意味でね、日本の美大出た人と僕とは違ったタイプ。メカデザインなんて感覚がね、弱い、美術学校出た人はね」
高橋「そういう分野がなかったしね」
沼本「なかった。で、そういうインダストリアルデザインに近い方の勉強をね、そういうのを自分なりに勉強したというのが強みなんだよ。それでまあ僕の役割というのは企画の方だと‥‥。みんなに評判悪いけど、植村伴次郎社長の言葉ってのは非常に重みがあった。金を儲けると。虫プロの時には儲けるという言葉はない。で、そういうこと言ったら軽蔑される(笑)」
高橋「まあそういう雰囲気ありましたね」
沼本「でも、お金を儲けなければ継続しないってことを身を持って知ってしまったからね。そういう意味では非常に敏感だった。メカデザインっていう概念ってものを伴次郎社長は知らないけども、[サンダーバード]ってものが売れたと。それを子細に説明してくるわけですよ。彼はあの時点で日本もそういう流れをこれからたどるということはわかってたね」
高橋「うーん、なかなかですね」
東北新社の総帥でもある植村伴次郎氏はある意味で立志伝中の人である。立志伝中の人なんていうものは毀誉褒貶が激しいのは通り相場で、植村氏もその細身の体型からして、『あのバンジロウガラスが!』などと呼ばれるのを社の内外でよく耳にしたものである。
沼本「で、僕としては[サンダーバード]の日本版にして、新しい点はどうしようって、いろいろ考えてでっちあげたというのがゼロテスター。それがサンライズのオリジナルの源流。これははっきりしてる。企画担当は僕がやってたから」
高橋「最初に[ハゼドン]ってあったでしょう。で、僕は何となく単純にね[ハゼドン]はきっとフジテレビの御祝儀だろうと。だから、その次からはねサンライズが何を作るかっていう方向が話しあわれて、それがまあ[ゼロテスター]だったんだろうと。で、それはサンライズの創業の7人ではなく言いだしっぺは伴次郎社長!?」
沼本「伴ちゃん」
高橋「植村伴次郎社長だったのかあ!」
沼本「だからまあ、SFをやれって伴次郎社長が言ったんじゃなくて、[サンダーバード]みたいな儲かるものをやってくれと。ということで[サンダーバード]のおいしいところをいろいろ集めたわけだ。だったら日本版の[サンダーバード]を作ろうという話しに、自然とね。僕も他に企画やる人がいなかったから。っていうよりも最初の3人以外は半年以上後だよね、サンライズスタジオに入ってきたのが。他の連中はまだ虫プロにいたんだから」
高橋「じゃあ、きっちゃんと沼本さんとそれから丸たん以外は‥‥」
沼本「丸たんはシナリオだからたまに来るだけだから。常時いたのはむしろ半藤、彼の方が多かった。半藤の世話で広岡氏があの頃制作で入ったんじゃなかったかな。忘れたけど。まあ本当にそういう手作りの時代で。スタジオと言っても最初はスケールの小さなミニチュアみたいなものだった。それで[ゼロテスター]をもっと大々的にバンダイが展開するはずだったのが、あの時ちょうどオイルショックで材料がどーんと値上がりしたために、プラスチックのね、玩具ってのはプラスチックの塊だから。それで企画がスケールダウンした。でもまあ[ゼロテスター]って売れた」
ダグラム、ボトムズ、ダンバイン、
ザンボット3、ガンダム、サムライトルーパー
僕の玩具のノウハウが入っているんです
高橋「沼本さんが抜けた後、山浦さんが企画を引き継いだ」
沼本「そう。でも厳密に言えば山浦さんは企画コーディネータ。ちょっと概念が違う。で、だからそういう意味でデザイン的なものとか、何だかんだサンライズがオリジナルやりだして、ダグラム、ボトムズ、ダンバインだかの中頃まで僕が監修したわけだ。ザンボット3とかガンダムとかあの辺は全部僕の玩具のノウハウが入っているっていうことですよ。その後いったん切れて、間があって又サムライトルーパーが僕の企画なんですよ」
高橋「そうですよね。僕もあれはちょこっと手伝わされたから。僕はほらいつもちょこちょこ手伝わされるんだ」
私にしてみれば[ゼロテスター]も[サイボーグ009]もダグラムの最初の頃も、虫プロの先輩に呼び出されてムリクリ手伝わされたという思いが強かった。まあそれが私の今に繋がっているのだけれど‥‥。
高橋「ところで、沼本さんはなんで早々にやめちゃったんですか、サンライズを。これずーと聞きたかったんですが」
沼本「いや、だから玩具の勘所が知りたいというのが先ずあるじゃない」
高橋「それは、ようするに沼本さん個人の望み?」
沼本「そう。それともう一つは立体物が好きだったと、平面よりね」
高橋「あ そうなんですか。やめてすぐタカラですか」
沼本「タカラへ行った。彫刻のまねごとみたいなことも学校へ行ってた頃やってたしね」
高橋「僕がお聞きしたいのは沼本さんが本当に言ったかどうかは別にしてあの頃『サンライズは出てもスポンサーで作品作れるようになってくるから』って言うようなことを言い残したとか」
沼本「そう、それは言ったよ。だから、その後かなりいろいろレクチャーしてるから。情報流してやったから。その頃サンライズはまだ作品を作る信用がなかった。で。まあ山浦さんが言ったと思うけど山浦さんがロボットの最初の頃ね苦労したわけだから。方向性は俺が出したけど苦労は山浦さんがしたのね、最初。ロボット路線だけはよそのプロダクションがやりたがらなかった、作るのが大変だったから。で、サンライズは玩具屋の手先になって頑張ると。何を言われてもかまわないんじゃないかというのが合い言葉みたいなものだった。それが玩具の主流になりアニメの売り上げの主流になるとは誰も予測しなかったね。ただ、僕はね、その可能性の方を見てた。その頃主流のスポンサーはお菓子屋さんだったわけですよ。明治や森永の1社提供とか。それがね、1社提供出来なくなってきて、人気がね、大体のアニメ作品が1年ぐらいで終わるようになっちゃって」
高橋「そういう時代に入ったんですか」
沼本「じゃあ、もうちょっと夢って何だろうっていうことになると、やっぱし、ぬえの連中なんかと話をするとさ、展望が開けるのね。だから山浦さんが僕のあとぬえを上手く使っていってくれた。で、ぬえは並行して僕がタカラの中でオリジナルの玩具のデザインをずっと出していくのに付き合ってくれた。そうすることがやっぱ、よそよりも一歩早くメカデザインというものに対する考え、つまり先見の明が生まれるってもんじゃない。そういう環境があってぬえは他より有利に展開できた」
高橋「ぬえかあ‥‥。[ゼロテスター]のときは、まだ松崎君なんかも絵を描いていたんだよね」
その後山浦さんが新潟のSFマニアの学生を見出し[ビシャル・デザイン]というグループ名でレイズナーの企画を立ち上げたのが私の記憶に残っている。その後ビシャル・デザインは解散したが、メンバーのうち2人はサンライズに入社し、今は中堅幹部としてサンライズを支えている。かく言う私の[リョウスケ塾]もその顰に倣って始めたものであるが結果はまだ出ていない。
美学より採算ベース…
どうやって客を掴むのか…
沼本「ノウハウを蓄積することが大事ですよ。だから組織から離れても僕なんかみたいにずっと生きていけるっていうか、もうここの事務所で17年か8年かやってるわけだから。何とか曲がりなりにね、やっていけるし。やっぱノウハウを蓄積するということはね、努力すればみんな公平にチャンスあるんです」
高橋「そうですね、チャンスはね。山浦さんなんか結果的には運が一番大きいっていうんだけれどもサンライズの創業からの方向性としてはガンダムならガンダムの成功みたいな方向を向いて進んでいっていたって感じがある」
沼本「植村伴次郎社長ですよ。実のところ、みんな拒否反応を示してイヤでしょうがなかった。そりゃ普通の人だったら逃げ出すんじゃないの、強烈なところがあるから。だから運命づけられた部分というのはそこにあるわけ。人あたりのいい人が最後までいいわけじゃなくて、悪い人の方が後々いい影響を持つということもある」
高橋「なるほど。沼本さんは植村社長と出会ったところで一番影響されたのは商売のある種の面白さみたいなものですか」
沼本「というより、そうしないとやっていけない。そんな美学だとかさ青春だとかロマンだとかそんなもの以前にまず採算ベースをやっぱり考えないといけない。そのため重要なのは、どんなことやって客を掴むのかということですよ」
高橋「具体的には?」
沼本「それは何かというと、[サンダーバード]以降の日本の作品の中で、永井豪さんがロボットもの創ったけども、ほとんどメカものってなかったわけだ、漫画の原作に。だから、やっぱり玩具屋が喜ぶような企画を創るというとオリジナルを創らざるを得なかった。原作ものがなかったからね。だから、そういうふうになったんであってね。そんな、メカものが好きでどうのこうのと言ったって、メカものは作るのキツイからね、誰でもがイヤがるパターンだから決して自然発生的に出来るもんじゃない。でも需要はあった」
美学より採算ベース…
試みを常に意識していれば
可能性はある
高橋「需要があるのに応えるところがなかった」
沼本「そう。それに対してチャレンジする勇気は大手プロダクションにはなかった」
高橋「まあ、タツノコが比較的そういう中では頑張ってましたよね」
沼本「うん‥。やがて変形に行き着いた。[ダイターン3]で変形をやったんですよ、僕が。それが最初なの、変形ものの。で、その変形ものっていうのがマッハ・パトロール、パトカーが戦闘機に変形するっていう。自分で粘土原型を造っていろいろ考えたあげく、これならいけるだろうって。粘土でこうやって造ったやつを大河原さんのところへ持っていって、これでデザインやってくれ、と言ったわけです。そこから変形ものっていうのがずっと拡がっていったっていうか定着していった。だから、新しいチャレンジ、試みを常にみんな意識していればね、まだ可能性はあるんじゃないかと思う。何が新しいものかということをちゃんと捉えられるかどうかが問題だけどね」
前回、変形に関しては山浦さんがパチンコのチューリップの開閉にヒントを得てライディーンで変形を試みたという発言があったが、沼本氏の趣旨は本格的変形と言う意味とに捉えたい。
高橋「沼本さんは僕が虫プロで最初であった時はアニメーターだったじゃないですか。それから一時僕の記憶の中では制作か演出かって揺れている時があって、それで制作。その後虫プロを退職し、サンライズの創業に立ち会って、それから企画やって、で、メーカーに就職して、まあメーカーの中で企画や開発をやって、またメーカーを退社したあと市場調査やったりとかしていましたよね。そういう中で、何が一番面白かったですか。または自分に合っているものとかは」
沼本「あのね、合ってるとか合ってないとか後で判る。‥‥もう苦労して苦労してね、やってるっていうようなのはやっぱしね実は合ってないんだよね。合ってるっていうのはマイペースで適当にやっててもひとりでに1クラス上の結果がでるとかね。これが合っているということですよ」
高橋「それは才能ってことですか」
沼本「才能とまで言うかどうかわからないけれども‥‥」
高橋「まあ、才能あっても苦しむ人もいますものね。一概に言えないかもしれないし。そういうなかではどうだったんですか? 何が一番自分ではあってると、後から考えると」
沼本「やっぱり企画だと思うね、僕は」
高橋「じゃあ、企画と、先程おっしゃった企画コーディネータとの違いというのはどういうところなんですか」
沼本「企画ってのは自分からオリジナルなものを提案していくことでしょ。企画コーディネータというのは、企画のなかでも戦略的な形になるんです。で、戦略的な形というのはこの分野のここを誰にお願いして、この分野のここは彼にお願いしてと、そういう、今流に言えばコラボレーションですね」
高橋「じゃあ、仮に[ゼロテスター]って素材があったら[ゼロテスター]そのものが沼本さんが考えて、[ゼロテスター]をどう展開していくかっていうことに関して言うと山浦さんみたいな人が合ってるってことになる」
沼本「ま、そういうことだな」
高橋「なるほど‥‥」
沼本氏へのインタビューは企画以外のテーマにも及んで有意義な意見をたくさん頂いたが、私には次の言葉が強く印象に残った。
沼本「今はアニメプロダクション全部が平準化してきているね。‥‥結局大きな投資をして大きなプロジェクト組む、それが成功する第一の条件なんだね。また、ここへきて状況そのものが厳しい状況というか、‥‥壁にぶち当たっているというのがアニメーション業界じゃないかな。多分今年から来年にかけてプロダクションが沢山潰れるんじゃないかと思う。目標というか目的ってものがないところで、徒にやっているという部分あるから‥‥」
自分に言い聞かせるように、つぶやくように言う氏の予測だが、こればかりは外れてほしいものである。
ま、とりあえずインタビューも終わったことだし、懐かしの高田馬場だ『こいつは只では、帰えーられめい!』と言うわけで、さてどこへ行こうかなっと。次週へつづく。
【予告】
次回は、(株)エムイーエス常務取締役:岩崎正美氏の登場!! 創業者の一人であり、数多くのサンライズ作品のプロデューサー。虫プロ時代から制作畑一筋!制作秘話を交えて創業から現在までを語ってもらった…。
【リョウスケ脚注】
栄通り
栄通り高田馬場の早稲田通りを早稲田方面からJRのガードを西にくぐってすぐ右にあるのが[栄通り]である。その昔極めて近い場所にスタジオあかばんてんがあった。通りの一番奥にある今では大きく立派になってしまい支店も数軒構える[鳥やす]が5、6人しか入れないカウンターのみの焼き鳥屋で奥の席に入るには全員が一度店の外に出なければならなかったぐらい昔のことである。その並びにある[双葉]ともどもあかばんてんは当然、サンライズ初代社長の岸本氏御用達の店であったが……両店ともに同じ酒同じぐい飲みを使用していた。大きく肉厚のぐい飲みの底に揺らめく二重丸の模様が懐かしい。
スタジオあかばんてん
私ことリョウスケが[ゼロテスター]終了年の1975年から1990年まで新宿区高田馬場で主宰していた同人的アニメーションスタジオです。東京で一番甘ったれた集団を自負していまして、ベタベタグズグズ、仕事場のような簡易宿泊所のような、インスタント食品の置き場所のような‥‥絶対に発展拡大はしないぞ、が全員の合言葉の面妖なスタジオでありました。あそこに行くと人間がダメになるとも言われておりましたが、一種のユートピアだとも言われました。ひょこっと飽きがきてやめてしまったのですが、幕の引き方もだらしなくて、らしいかなと思っています。
山浦さん
その昔この人の体重が98キロもあった時私の体重は58キロだった。今では私は74キロで氏は65キロ。この体重の推移がお互いの人生の過ごし方を物語っているか……。私がアニメーションを去ろうとしていたのを強引に引き戻してくれた、ある意味の恩人。サンライズの第三代社長である前に酒仲間でありゴルフ仲間であり馬仲間でもある。これと言って欠点のない人だが、どんな高価なスーツやネクタイを締めていても食べ物をポロポロペチャペチャこぼすのは、どうにかなりませんかね。奥さんが泣いています。
きっちゃん
初代社長の岸本吉功氏の愛称である。岸本氏はだいたいのところこの[きっちゃん]の愛称で呼ばれていた。奥様も生前からそのように呼んでいて、たまに思い出話などされるときには「きっちゃんがね……」などと遠い目をされる。ごくまれに古い知人に[よっきり]と呼ぶ人がいるが、これは[岸本吉功]を[岸本吉切]と読み間違えた人達で、その人たちは間違いを訂正せずフルネームでは[きしもとよしきり]と言い普段は[よっきり]と呼び続けていた。きっちゃん自身もあえてそれに異議を申し立てることはなく、そう呼ばせていたのが今は懐かしい。
丸たん
ご存知[マッドハウス]の総帥、丸山正雄氏。リョウスケとはほぼ虫プロ同期の桜である。ま、両方とも桜って柄ではないが……菊池寛に似た飄々とした風貌で、今や日本で一番ではないかと言う制作量を誇るプロダクションの経営から企画、プロデュースまでを何気なくうっちゃるようにこなしている。阿佐ヶ谷は中杉通りにあるコジャレた和風フレンチレストラン[風羅坊]のオーナーにしてギャルソンの顔も持ち、時により河岸に仕入れにも行けばお仕着せにて店にも出ると言う趣味人。ま、ある種の怪物です。
半藤
フルネームは[半藤克美]氏。日本のテレビアニメーションの美術背景を開拓した人といっても過言ではない。リョウスケの虫プロ入社と入れ替えのように退社し[東京ムービー]の創立に参加し、その後(有)スタジオ・ユニを創設。数々の人材を輩出している。[ゼロテスター]制作時には[河野次郎]と言う活きのいい美術監督を推薦していただき、背景を全面的に引き受けてくれた。アニメ界の主のような人で業界の人事部長とも称されている。普段多少吃音気味のところがあるのに、その昔スタッフが司法の裁きに立たされたとき弁護側の証人として出廷し、論旨明快、滑舌明瞭、実に堂々たる論陣を張ったと言う逸話を持っている。
箕輪氏
フルネームを[箕輪宗廣]氏。当時都立家政に住んでいた。お宅に伺うと部屋のいたるところに人生訓や処世訓などの扁額が掛けてあり、それらの指し示す教え通りに生きようとしていた、まじめと言えばまじめな、ちょっと変わった人ではありました。あるときつまらぬ誤解がもとで大喧嘩となり、互いに意地を張って都立家政には行かぬ、上井草になんか顔を出したくないと言い張って、間を取って鷺宮の喫茶店で対決し、大人気なく罵り合ったことが昨日のように思い出されます。むろんその後は誤解も解け、よきパートナーとして仕事を楽しみました。メデタシメデタシ。