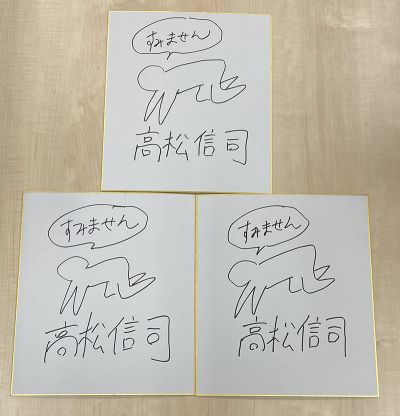特集
SPECIAL
- インタビュー
クリエイターインタビュー 第6回 高松信司 <前編>
「勇者シリーズ」のインタビュー企画第2弾は、『勇者特急マイトガイン』、『勇者警察ジェイデッカー』、『黄金勇者ゴルドラン』の監督を務めた高松信司さんが登場。前編では、サンライズでの初期の仕事歴、そして恩師でもある谷田部勝義監督と一緒に関わった勇者シリーズの立ち上げとその後への繋がりを語ってもらった。
――高松さんはどのような経緯でサンライズに入られたのでしょうか?
高松 学生時代は映像作品を作りたくて8mmカメラばかり回していて、あまり学校にも行っておらず…(笑) 映像の仕事をしたいという思いもあって大学を中退したんです。ただ、映画やテレビなんかの映像の仕事はなかなか入れてくれるところが無くて。でも、当時のアニメ業界はわりと簡単入れてくれたんです。それであちこち回るうちに、『装甲騎兵ボトムズ(以下、ボトムズ)』のプロデューサーを務めていた長谷川徹さんを紹介していただく機会があって。それがきっかけで1983年の夏に欠員募集で、当時まだ「日本サンランズ」にぬるっと入りました。そして、第1スタジオの『ボトムズ』班に配属されるんですが、ちょうど、「クメン編」をやっている時で、特に研修とかも無くいきなり現場投入させられた感じですね。そこで、入社初日から家に帰れないという経験をしました(笑)。
――いきなり過酷な形でスタートされたんですね。
高松 『ボトムズ』をやっている間に後番組の制作がスタートするんですが、それが途中でポシャってしまい、『ボトムズ』終了と共に1スタが一時解散になりまして、それで、『銀河漂流バイファム』を作っていた3スタに出向して2本くらい制作を担当していました。その後『機甲界ガリアン(以下、ガリアン)』が動き始めて再び1スタに戻りました。そして、『ガリアン』が終わる頃に、2スタのプロデューサーの内田健二さんに『機動戦士Zガンダム(以下、Zガンダム)』に誘われて、設定制作として2スタに異動するという流れで、富野由悠季さんの元に行くことになりました。
――アニメの仕事を始めた時は、演出を希望されたりしていたんでしょうか?
高松 若者特有の根拠のない自信で(笑)将来的には監督になりたいと思っていましたね。『ガリアン』をやっていた時、同じ建物の2階が2スタで、当時『重戦機エルガイム』をやっていて、そのデスクだった内田さんに、会う度に「演出やりたいんですよ」みたいな話をしていたんです。そんな時に『エルガイム』の設定制作をされていた方が辞めるということになって、その後任にと、内田さんから声をかけてもらった感じですね。設定制作は監督直属の制作で、そこから先輩たちが何人も演出になっていったので一も二もなくでした。
――富野由悠季監督の現場はいかがでしたか?
高松 『Zガンダム』の頃は、富野さんが最もエキセントリック(苦笑)だった時期なので、大変でしたね。私は、設定制作と文芸も担当していたので、シナリオ打ちの段取りから設定の発注までやっていたんですが、1年間毎日富野さんにどやしつけられていました。でも、富野さんの仕事を近くで見ることができたのはすごく勉強になったし、ガンダム作品の中で演出デビューできたのでそれはすごくありがたかったですね。その演出デビューも、急に演出さんがいなくなってピンチヒッターが必要になり、「誰か演出いない?」という話になった時に、それこそ若者特有の根拠のない自信で「やりたいです!」と手を挙げて。それが、第31話の「ハーフムーンラブ」でした。当然、全くの初めてなので、編集さんや音響さん、もちろん富野さんにも「なってない」って厳しく言われた、かなり苦いデビューだったんですが、それをきっかけに『機動戦士ガンダムZZ(以下、ガンダムZZ)』ではレギュラーでコンテ、演出を担当させてもらうようになりました。今思えば、全くの素人をよく使ってくれたなと思います。
――その後はどのような流れで勇者シリーズに繋がっていったのでしょうか?
高松 『ガンダムZZ』が終わって、ガンダムから脱出できるかと思ったら『逆襲のシャア』でも演出補で捕らえられてしまって(笑)。ただ、劇場版なので準備に時間がかかっている間に、1階でやっていた劇場版『ダーティペア』が大変だというので、援軍に行ったんでが、その演出が谷田部勝義さんだったんです。谷田部さんとは、制作進行としては担当させてもらっていたんですが、この時はじめて演出助手として仕事をさせてもらい、その後、谷田部さんが初監督した『ダーティペア』のOVAで各話演出で呼んでもらいました。そして、『勇者エクスカイザー(以下、エクスカイザー)』が始まる前に、「こんな番組をやろうと思っているんだけど」と企画書を見せてもらって、「これ、やります!」と食いついたのが、勇者シリーズの参加に繋がっていったという感じですね。
――『エクスカイザー』の企画には惹かれるものがあったんですね。

高松 本当に『エクスカイザー』が大好きで、「こういうのがやりたかった!」という気持ちがありましたね。谷田部さんはわりと自由にやらせてくれる人で、各話の敵のデザインや色々なアイデアなど、「こんな風にしたい」をみんな受け入れてもらえて。でも、企画に参加したという意識はないんです。だだ、喋ってただけです。とにかく『エクスカイザー』は楽しかった。それが、『太陽の勇者ファイバード(以下、ファイバード)』になると、谷田部さんも言っているかもしれませんが、高松がだんだん文句を言うようになってきて(笑)。今思うと、『エクスカイザー』が好き過ぎて、『ファイバード』には拒否反応があったのかなと思いますね。大人げないというか……。『エクスカイザー』は、本当にプリスクールの子供に向けての作品として完成されていたと思うんです。でも『ファイバード』はいろんな大人の事情も入ってきて、物語も絶対悪VS正義みたいな方向へとシフトした感じがあるんですよね。その辺りが肌合い的に受け入れがたかったのかなと思いつつ、あんなにゴネなくてもいいよなと(笑)。それで、『ファイバード』の制作に入ってしばらくすると、『伝説の勇者ダ・ガーン(以下、ダ・ガーン)』の企画が始まるんですが、谷田部さんから「そんなに文句を言うなら、やる方に来い」と言われて、それでチーフ演出として参加することになったんです。『ファイバード』までは各話演出で参加してシナリオや設定に文句言っていたわけですが、『ダ・ガーン』でチーフ演出になってシナリオ打ちとかに参加するようになると、文句も言えなくなるでしょうと。
――制作におけるいろんな事情が見えてくるということですね。
高松 実際にライターさんと打ち合わせをして、局や代理店、スポンサー側からの意見を聞いて、作品に落とし込んでいく。それは本当に勉強になったし、実際に自分が監督になった時に、監督と各話演出ではやることが全然違うのがわかって、その時の経験がすごく生きましたね。そうしたことを何も知らずに、急に監督になって、何もわからない状態で矢面に立たされたら多分大変だったと思います。
――作品を作る上では、いろんな根回しなども必要になってきますからね。
高松 谷田部さんはネゴシエーションの人なんですよ。交渉して何でも解決してしまう。あれは才能だなって思いますね。和を以て作品を作っていくというような感じで。それは私にはできなかったです。富野さんは、シナリオもコンテも全部自分でやりたい人なんですよね。でも、谷田部さんはみんなの力をうまく使って、自分は飲みに行く(笑)という人で。それこそ、『エクスカイザー』の第1話のコンテを福田己津央さんに振っているんですよ。初めてのTVシリーズの監督をやるのに第1話を人に振るというのが凄いなと。
――谷田部さんは、自分は勇者シリーズは3本で終わって、次は高松さんに任せるつもりだったという話をされているのですが、そうした話を御本人と直接されたりはしたのでしょうか?

高松 私的には「次、やらせてもらえる」というような約束もしてなかったです。確かに、『ダ・ガーン』をやっている途中で、次の企画を何か出して欲しいと言われたんです。その時は、私は企画コンペだとと思っていたので、勇者シリーズのつもりではなく、ここに「勇者」と同じ乗物がロボットになる玩具があって、これをアニメにするとしたら私ならこうします……という企画書を書いてサンライズに出したんですよ。当然、コンペとして、いろんな人に声をかけていると思っていましたし。そうすると、プロデューサーの吉井孝幸さんが「じゃあ、次は高松ちゃんが監督ね」と言われて。谷田部さんはそのつもりだったのかもしれないですが、私は何も聞かされていないので「え?」って感じで。あんなに文句を言っていたのに、ついに自分でやらなければならなくなってしまった(笑)だから、谷田部さんは本当に師匠と言って過言ではないです。谷田部さんがいて、勇者シリーズがあって、ラインを引いてくれたその跡を継いだので。そこは、純粋に尊敬する先輩であり、師匠だと思っていますね。
――ちなみに、谷田部さん以外でサンライズで仕事をしながら影響を受けた方はいらっしゃいますか?
高松 やはり富野さんは師匠ですね、不肖の弟子ですが。当時「富野学校」と言われる、いわゆる名古屋テレビ枠の番組から演出家がどんどん出て来たわけですが、私はそこを卒業する前に終わってしまったので、弟子を名乗るのはおこがましいですが。怒られてばかりいた記憶しかないですが、本当に勉強させていただきました。それから、高橋良輔さんは、演出として直接教えを受けたわけではないですが、進行の時から仕事をしている様子を見させていただいて、勝手に勉強させてもらっていました。良輔さんも人を使うのが本当に上手い方で、そういう意味では谷田部さんの師匠でもあるんですよね。『ボトムズ』の現場で衝撃だったのは、スケジュール的に厳しくてどうにもならなくなった時に「じゃあ、総集編を作ろう」と言い出して。「何話と何話のラッシュを焼いておいて」と言って、そのフィルムを切り始めて。総集編1本を1日で作ってしまう。それを1年に3回くらいやるんです。思い切りの良さ、それも凄いなと思いました。
――そして、今でも現役で活動されていますからね。
高松 演出協力とか総監督的なポジションでいろんな作品に関わられて。私は、勇者シリーズの後に『こちら葛飾区亀有公園前派出所』の監督をやるんですが、それも、その時『ガオガイガー』でプロデューサーをしていた良輔さんが、スタジオぎゃろっぷに紹介してくれたんです。ぎゃろっぷの社長も「良ちゃんがいいというなら」と起用していただきました。良輔さんは、「俺が責任持つから」と言って、基本は任せてもらえるし、トラブルがあれば出て来てくれる。そういうところが信頼されているところであり、私にとっても恩人ですね。
高松信司(たかまつしんじ)
1961年12月3日生まれ、栃木県出身。アニメーション監督、演出家、脚本家、音響監督。
1983年に制作進行としてサンライズに入社。設定制作、選出助手を経て『機動戦士Zガンダム』で演出デビュー。勇者シリーズには第1作目『勇者エクスカイザー』から参加し、第3作目『伝説の勇者ダ・ガーン』で演出チーフ。第4作目の『勇者特急マイトガイン』から、『勇者警察ジェイデッカー』、『黄金勇者ゴルドラン』までの監督を務める。『機動新世紀ガンダムX』『こちら葛飾区亀有公園前派出所』、『銀魂』などを監督。『銀魂』では音響監督、『男子高校生の日常』では監督、脚本、音響監督も務めている。
インタビュー掲載記念でサイン色紙をプレゼントいたします。
詳しくはプレゼントページでご確認ください。