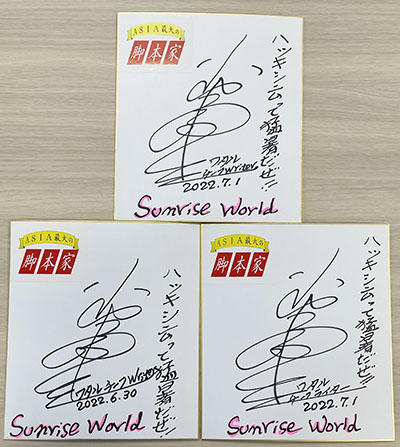特集
SPECIAL
- インタビュー
クリエイターインタビュー第10回 脚本家 小山高生<後編>
2023年に35周年のアニバーサリーを迎える『魔神英雄伝ワタル』。現在も根強い人気を誇る『魔神英雄伝ワタル』のキャラクター造形の一翼を担ったのが、チーフライターとして脚本作りのメインとして関わった小山高生さん。『魔神英雄伝ワタル』への関わりを伺うインタビューの後編では、監督の井内秀治さんとの思い出、シナリオ制作におけるこだわり続けた要素などについて話を伺った。
――監督の井内秀治さんとのやり取りについては、どんなことが印象に残っていますか?
小山 井内さんという人は、ギャグに向いている人じゃないんだよね。すごく真面目な人で。だから、僕と組んで良かったんじゃないかな。演出が、僕のやっているバカなことに引っぱられていたりすると統一性がなくなってしまうし、やっぱりお話としてはシリアスな部分も必要なわけで。そのメリハリで面白さを倍加していく部分があるから。井内さんがああいうシリアスな部分で演出しているというのがあったから良かったんじゃないかと思う。だから、制作中は僕とはぶつかる部分が多かった。すごくこだわる人でね。粘着質なこだわりをする人だから、シナリオの直しがたくさん来る。「ここはギャグでやっているんだよ」と言っても、なかなか引いてくれなかったりしてね。でも、そうしたやり取りがあったからこそ、作品がうまく立ったのかもしれないです。
――やはり、少年が真面目に成長するという部分も作品としては重要ですからね。

小山 僕はすぐに遊んじゃうから、彼がその部分をうまくブレーキをかけてくれていたという感じで。そういう意味では、逆に趣味趣向が合わないところが良かったんじゃないかな。虎王の悩みや苦しみみたいなところは、僕はあまり書きたくなくて、キャラクターたちにバカをやらせたい。だから、あれは井内さんらしさなんだよね。一方で芦田さんは何でもできちゃう人だから、お任せしちゃえばいいという部分があるんだよね。自由にやってもらった方がいい。だから、時々とんでもないことをやってしまうけど、決まった時の絵の凄さというのがあって。芦田さんは、融通の利く仕事ぶりが作品に与えた影響は大きくて、だから本当にピースとして井内さんがいて、芦田さんがいなかったら、『ワタル』になっていないだろうなと思うね。
――『魔神英雄伝ワタル(以下、ワタル)』はロボットアクションものでもあるわけですが、そこに関してはどんな意識を持っていましたか?
小山 僕としては、メカ戦に関しては『タイムボカン』シリーズのノリを結構知らず知らずのうちに出してしまって。やっぱり、僕はタツノコプロのギャグで、タツノコプロのギャグは笹川ひろしさんのギャグであり、エスカレートしていくギャグの見せ方なんです。ある意味関西風のギャグ。徹底したサービス精神のギャグで、江戸の粋なギャグじゃない。だから、『ワタル』ではそこの浪花節的な部分をシバラクという存在を入れることで、クサイ芝居をできるように作っておいたということがあって。それが上手くいったのかもしれないね。
――キャラクター配置の妙みたいなものも、作品を彩る重要な要素でしたね。
小山 クラマを演じてくれた山寺宏一さんは、当時から芸達者で物真似がすごく上手で、そういうところはクラマというキャラクターの造形には大いに役立ったね。クラマという役は難しかったと思うんだけどね。当時、山寺さんは今のように売れっ子の時期じゃなかったけど、ワタル役の田中真弓さんとヒミコ役の林原さんが縦横に演じているところにうまく入り込んで、その辺りのピースのハマリ方も良かった。ああいういい形でハマるメンバーを集めるというのもなかなか難しいからね。龍神丸を演じた玄田哲章さんは、僕が脚本に参画した「アラレちゃん」ではスッパマン、『昭和アホ草紙あかぬけ一番!』という作品で、ヒカリキンという馬のキャラクターを演じて、最高のギャグをやってくれた人なんだけど、『ワタル』でも一緒に仕事ができた。不思議と縁のある人と繋がった感じがするんですよ。
――『ワタル』に関わっていた当時、ファンの反応などは聞こえていたのでしょうか?
小山 最初は夕方5時に放送ということだから、小学校4年生くらいをメインターゲットにしていたんじゃないかな。それが意外なことに上の年齢のファンに広がって、虎王が出てきたら女の子たちが大騒ぎし始めていたわけでしょ? その辺りは全然計算外だったよね。でも、放送時の視聴率はそこそこいっていたし、ターゲット層が買うオモチャも売れていたわけだから、そこは全然問題なかったんじゃないかな。
――だんだん、アニメ好きの中高生の女性ファンが増えていった印象はありますね。
小山 放送終わった後にラジオ(『ラジメーション 魔神英雄伝ワタル3』)があったりして、そうした広がりも大きかったんじゃないかな。そういう意味では、こちらが全く意図しない形で、計算外のパワーが産み出されていた部分があったんだよね。
――お話も小学校4年生くらいが楽しめるものとして書かれていたわけですね。
小山 お話作りで意図したものは、徹底したサービス精神。ギブ・アンド・テイクじゃなくて、ギブ・アンド・ギブ。引き出しの中にアイディアがあったら、全部1回で使いきっちゃえという精神。使い切れば、また引き出しに新しいアイディアが入るぜという感じ。僕の教え方は、「アイディアの出し惜しみなんてしたら、お前の実力じゃ面白いものが書けるわけがない。今、思い付いているアイディアは、次回使おうなんて思わずに、今、全部使え」というものなの。ギブ・アンド・テイクの「テイク」なんか考えるな。テイクはあとからついてくるものだから、徹底してサービスしろ。お茶の間の子どもたちに徹底したサービスをして、ひと時憂さを忘れさせればいいんだよ。大人はお酒を飲んでストレスを解消できるけど、塾通いの子どもはそうはいかない。そういう気持ちで書いていましたよ。
――小山さんは『ワタル』という作品に対してはどのような印象が残っていますか?
小山 僕はあの頃「ギャグの小山」って言われていたんですよ。そういうレッテルを貼られると、日本ではなかなか剥がせないじゃないですか。それで、来る仕事がずーっとギャグものしかないという時期があったんです。そんな中で、『聖闘士星矢』の仕事が来て。まだ漫画の連載が始まってそんなに経っていない状態での依頼で、先の展開もわからない。だから上手くやれる気がしなくて「これはアクション専門の人がやった方がいいよ」と断ったんだけど、依頼をしてきた東映の横山和夫さんというプロデューサーが「小山さん、よく見てください。原作は笑っている顔がひとコマもないんです。この作品をアクション専門の人に頼んだら更にシリアスなものになってしまう」と熱く語ってきて。要は、漫画の中に息抜きのシーンもないということなんだよね。「この展開の中に、小山さんがギャグを入れて、どう料理するのか見てみたい」と言われて、「なら、やりましょう」と受けたんです。その結果、原作にない星の子学園での子どもたちの生活の中で笑いを入れつつも本編を書き進めることでイメージを変え、以降アクションシーンの描写に励んで、ギャグ専門ライターだったのがアクションものも十分書けるようになった。そして、その後『ドラゴンボールZ』のシリーズ構成の依頼が来て、そこでギャグものもアクションものもどちらも書ける、両刀遣いになることができた。そんな仕事が来ている状態の中で、『ワタル』では再びギャグの方で感覚を研ぎ澄ますことができたし、新しい流れに乗れた。『ワタル』はそういう意味で出会うことができてとてもラッキーな作品ではありましたね。
――サンライズ作品では『勇者特急マイトガイン(以下、マイトガイン)』にも関わられていますが、こちらも思い入れがある作品なのでしょうか?

小山 そうですね。『マイトガイン』も本当に自由に作らせてもらって。マイトガインの口上を考えた時、プロデューサーの吉井さんから「ちょっと長いよ」と言われて調整した結果、「銀の翼に望みを乗せて……」という、なかなかいい口上ができたと自分でも思っていて。あれが出来て『マイトガイン』はうまく納まったなという感じがしましたね。やっぱり、口上とかが決まらないとキャラクターの造形が完全には終わらないので。僕はキャラクターを立てるためにはちょっとした癖をつけるようにしているんです。例えばワタルも龍神丸を呼ぶ時のいつもの口上の他に、「はっきし言って」みたいな口癖をつくると結構キャラクターがはっきりしてくる。第1話では、これからも毎回ずっと言い続ける戦闘時の口上と、キャラクターの特徴となる口癖みたいなものを悶々と探していて、いい言葉が見つかると物語の見え方が全然違ってくる。アニメーションのキャラクターは、生身の役者さんが演じるのと違うから、些末なことなんだけどそうやって肉付けしてあげると血が通っているキャラクターになる感じがするんですよね。だから、第1話を書く時は、ギャラに合わないくらいこういうところで苦労するんだけど、各話を担当するだけでは経験できない肉付けをできるところが第1話を担当するライターとしての醍醐味でもあり、役得でもある。そういう些末なことでもしっかり固めていくと、お茶の間への届き方が変わってくるし、まず自分が面白いと思ってないと楽しめないから。
――では最後にシナリオライターを目指している方たちにアドバイスをお願いします。
小山 アニメのシナリオライターは、徹底したサービス業であることを意識しておいてほしいね。サービス業だから、出し惜しみせず、どんどんアイディアを出して、自分たちも楽しんで書くように取り組んでほしいです。そうすると、絶対に時代が変わっても、見る子どもには伝わるから。やっぱり、アニメって子どものものだと思うんだよね。今みたいに大人世代が見るアニメがあってもいいと思うけど、やっぱり基本は子どもを楽しませるものだと思うし、そこを忘れないでほしいな。子どもが面白いと思うものは、大人が観ても絶対に面白い。だから、まず基本は子どもを楽しませることを考えた上で脚本を書いていくという姿勢が大事なんじゃないかな。僕も門下生たちにはいつもそう言っていたんだけどね。
――もともとアニメとは何だったのかをちゃんと考えてみるのも必要ですよね。
小山 そういう意味では、今は本当に子どもを楽しませる作品というのが減っているんじゃないかな。それは残念ですよね。そうなるとライターも腕が鈍るというか、子ども向けのものが書けなくなってくると思うんですよ。やっぱり、子どもの目ってシビアなところもあるから。ごまかせない。子ども魂に訴える作品もあるけど、子ども騙しはダメだと。子ども相手だからこそきちんと子ども魂に訴える作品を作らなくちゃいけない。そこは心に留めておいてほしいですね。
小山高生(こやまたかお)
1948年4月21日生まれ、東京都出身。脚本家、作家。
1972年に竜の子プロダクション企画文芸部入社。「いなかっぺ大将」で脚本家デビューし、「タイムボカンシリーズ」など多くの作品の企画や脚本を担当。1975年退社し、フリーとなる。1986年夏「アニメシナリオハウス」開講。1987年企画創作者集団「ぶらざあのっぽ」を創立(25年間活動し、60人余りの脚本家をデビューさせる)。
サンライズ作品では『超力ロボガラット』『魔神英雄伝ワタル』(チーフライター)、『魔神英雄伝ワタル2』(シリーズ構成)、『勇者特急マイトガイン』(チーフライター)などがある。
現在脚本家デビュー50周年を記念して74歳でYouTuberデビューし、毎週1回更新を続けている。小山高生 アニメのT王チャンネル
https://youtube.com/channel/UCSGeufSJz2qxzwCfDk9w0HA
チャンネル登録 ぽちっとな!!
<前編>はこちら
インタビュー掲載記念でサイン色紙プレゼントを実施中!
(2022年7月31日(日)23:59まで)
詳しくはプレゼントページでご確認ください。